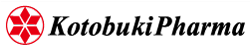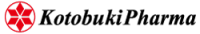1.大腸憩室とは
憩室とは腸管の内壁の一部が外側に向かって袋状にとびだしたものです。内視鏡でみるとくぼみのようになっています。憩室の数はさまざまで、頻度は年齢とともに増加しますが、大腸検査を行うと10人に1人くらいの頻度で見つかります。
欧米人に多く、日本人にはあまりみられませんでしたが、最近は増加しています。とくに都市部のひとに多く、食事の欧米化、とくに食物線維の摂取量の減少と密接な関係にあると考えられています。日本人では盲腸や上行結腸など、大腸の右側に多くでき、欧米人では大腸の左側に多いという傾向があります。しかし、食事の欧米化や高齢化に伴い、日本でも大腸左側の憩室が増えています。
2.原因
腸壁そのものがとび出す真性憩室と腸壁の筋層のすきまから腸粘膜がとび出す仮性憩室の2種類ありますが、大腸憩室症の場合にはほとんど後者の仮性憩室です。腸管の内圧の上昇に伴い大腸壁の筋肉層の弱い部分(たとえば血管などが腸壁を貫いて筋層が弱くなっている部分)から粘膜が脱出して憩室が生じると考えられています。
3.症状
ふつうは無症状ですが、憩室に炎症をおこして憩室炎になると腹痛の原因となったり、出血することがあります。盲腸など右側の大腸の憩室炎は急性虫垂炎と症状が似ていて、鑑別が困難なこともあります。検査で大腸に憩室があるといわれた方は、このような病気を起こすかもしれないので、腹痛や下血で病院を受診した際の問診で大腸憩室があると(わかればその部位も)申し出るようにしてください。
4.診断
多くの場合は検査で偶然発見されます。胃のバリウム造影検査の数日~数週間後に腹部のX線検査を受けたときに大腸の憩室に残ったバリウムがみられ、憩室の存在がわかったり、注腸X線検査や大腸内視鏡検査を受けたときに偶然発見されることもよくあります。
憩室炎をおこしているときは、腹部CT検査や超音波検査で憩室の存在や憩室炎を診断できることもありますが、下部消化管の検査は治療によって症状がなくなってから注腸造影検査や大腸内視鏡検査を行って診断を確定します。
5.治療
大腸憩室症は悪い病気ではありません。たとえ憩室がたくさんできていても、症状がなければ治療は必要ありません。憩室炎や憩室の周りまで炎症が広がる憩室周囲炎は、放っておいて重症化すると腹膜炎に進展することもあり、抗生物質による治療が必要です。大腸憩室からの出血は多くは間欠的な出血で7~8割が自然に止血しますが、出血の程度が重度の場合やくり返す場合には大腸内視鏡による止血処置を行うこともあります。施設によっては注腸X線検査と同じように肛門からバリウムを注入して止血を行うこともあります。また、穿孔といって憩室に孔があくことがあり、こうなると腹膜炎をおこして緊急に手術しなければなりません。
大腸憩室症があっても、日常生活の特別な制限はありません。ただ、比較的線維分の多い食事の摂取を心がけるとともに、便秘をしないよう便通のコントロールを行うことも大切です。なんども憩室炎をくり返すと、大腸が細くなったり癒着を生じたりして、便やガスの通過が悪くなることがあり、便秘や腹部の膨満感が続いたり、大腸内視鏡検査の挿入が困難になったりします。